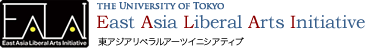2025年1月30日、大寒の候、清冽の駒場にて、第5回EALAI研究セミナーが開催された。発表者は、比較文学比較文化、および日本古典文学が専門で、絵巻物に描かれた顔の研究などを行っている永井久美子氏(総合文化研究科准教授)。テーマは「「世界三大美人」と「大正三美人」を繋ぐもの —— 和歌と「美人観」との関連性」であった。

「三大美人」とは誰か。本朝三美人、源平三美人、戦国三美人、寛政三美人、大正三美人、昭和三美人、世界三大美人。日本には古くから「三大」を選ぶ風潮があり、多くの「美人」が選ばれてきた。今回のセミナーでは、「世界三大美人」並びに「大正三美人」に焦点が当てられた。
「世界三大美人」といえば誰を思い浮かべるだろうか。クレオパトラ、楊貴妃、ヘレネが連想されるとすれば、その三人目の人選には、敗戦によるアメリカへの劣等感と憧憬、特に戦後のハリウッド映画『トロイのヘレン』の影響があるという(※1)。大正初期に「世界三大美人」の話が普及し始めた当時は、ヘレネではなく小野小町が数えられていた。「世界三大美人」に日本人を選ぶという発想には、日清・日露戦争勝利を経て、日本が西洋、及び中華世界に対抗できるとの思想が反映されていた。
ではなぜ、世界三大美人はクレオパトラ、楊貴妃に加え、小野小町だったのだろうか。
クレオパトラは、明治期に、翻訳の流行や新聞、雑誌の記事の影響でその名が知られ、プトレマイオス朝を滅ぼしたことから、19世紀末に人気を博した「運命の女 (femme fatale)」として改めて注目された。この「破滅を呼ぶ運命の女」を共通項として、唐を衰退させた楊貴妃が、「長恨歌」で平安時代から有名であったものの、近代にも脚光を浴びたと考えられるという(※2)。
この二人に対して、小野小町には、深草の少将なる人物の失命を招いたという伝承はあるものの、「傾国の美女」というほどの「魔性」は認めがたい。むしろ、百夜通いの少将にも逢わなかった「貞女」とする評価もあり、近代日本男性の理想的な女性観を体現していたともみられる。小野小町は、「運命の女」とは別の評価軸で選ばれたようだ。
永井氏は、「世界三大美人」選出と同時期に国内で話題とされていた「大正三美人」を分析することで小町選出の理由を読み解こうとする。西本願寺法主の次女で、公家に嫁ぎ「貞淑」で和歌に長じた九条武子、複数の結婚歴に加え、九州の炭鉱王との婚姻中に駆け落ちをした歌人・柳原白蓮、芸者で、夫の死後、自殺した江木欣々、舞踏家で、夫が他界した直後に再婚し話題になった林きむ子。スキャンダル性に富む女性が注目されたのは、「運命の女」を好む傾向の反映とみられる。一方で、武子や白蓮が人気を博したのは、名家出身の女性に対する憧憬からであり、白蓮に話題性が見いだされたのに対し、武子は夫の長期不在を守った「貞操」が高く評価された。同時代においてとりわけ人気が高かったのが武子で、貞淑で歌をよくした高貴な女性、という評価が、当時求められた「理想の日本女性」の枠に合致したとみられる。和歌は、諸芸の中でも別格であったようだ。
和歌と「美人」の結び付きは、5世紀、『古事記』『日本書紀』に名の記された允恭天皇の妃、衣通姫にまで遡る。輝くほどの美しさを誇ったという衣通姫は、和歌の神として祀られた。『古今和歌集』仮名序には「小野小町は、いにしへの衣通姫の流なり。」とあり、小町は衣通姫の子孫であるとする文献もあるなど、聖なる性質を小野小町に見出そうとする動きもあった。和歌は「日本独自の伝統文化」という位置付けを超えて、人を魅了する力を持つものとしても特別な意味を持ったようである。
本セミナーは、オンライン併用で開催され、一般の方から専門家まで多くの方が耳を傾けた。講演後には、お嬢様でもスキャンダラスな女性でもないような人物は「美人」に選ばれていないのか、「三大美人」選出の担い手は男性なのか女性なのか、女性にとっての和歌の意義、和歌と他芸術との差異等について、専門的な角度からの質問が多くあり、実り多い議論がなされた。また、「歌姫」という語の発祥や由来についても、今後さらに掘り下げるべき問題として永井氏は提起された。
加えて印象的だったのは、永井氏が、現代の表象に対しても関心を広く向けられていたことである。CM、Xのポスト、ChatGPT等の例を取り上げ、現代の美人観を炙り出していた。同時に、寛政の三美人を「会いに行けるアイドル」と呼称し、九条武子を「インフルエンサー」と紹介することで、現実性をもって生き生きと当時を感じることができた。
「大正三美人」を支点とし、「運命の女」と「歌人」という補助線が入れられることで、「世界三大美人」に小野小町が選出された理由が鮮やかに説明されていた。
個人的には、人選の背後に反映された思想、特にナショナリズムに興味を惹かれた。大正三美人の人選には「お嬢様」と「大衆」が綯交ぜになった様子が見られるという。確かに、公家に嫁いだ武子に対して、白蓮や欣々は親しみやすく大衆的と言える。しかし、E.H.カーによれば、1870年に始まり1914年以降発展した第3期ナショナリズムは、新しい社会層を国家の成員に組み込み、大衆の支持に基盤を置く「国家の社会化」をその特徴としている(※3)。だとすれば、大正三美人のみせた「大衆化」は、「世界三大美人」に小町を選出した流れを汲む、ナショナリズムの深化とみなせるかもしれない。
また、I.バーリンが指摘するように、ナショナリズムは「国民意識が火のように終え上がる状態」であり、「それは通常、傷 ——何らかの形態の集団的な屈辱—— によって惹起される」ものと考えられる (※4)。日清・日露戦争後のナショナリズムの昂揚には、明治期のナショナリズムの挫折があるだろう。だとすれば、永井氏の指摘する、戦後の「自主的な」小町からヘレンへの変更や、現代における西洋の美の基準の迎合は何らかのナショナリズムを醸成していないだろうか。世界を席巻する「きゃりーぱみゅぱみゅ」や「YOASOBI」といった「かわいい」歌姫の日本における強烈な存在感は、傷つけられたナショナリズムの横溢なのかもしれない。

参考文献
1) 永井久美子「「世界三大美女」言説と戦後日本の美人観——小町とヘレネの交代から考える」荒木浩ほか編『〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界』, KADOKAWA, 2021
2) 永井久美子『「世界三大美人」言説の生成:オリエンタルな美女たちへの願望』,HMC, 2020
3) E.H.カー, 大窪愿二訳『ナショナリズムの発展』, みすず書房, 1952
4) I.バーリン, 福田歓一ら訳「曲げられた小枝」『バーリン選集4 理想の追求』岩波書店, 1992
高山将敬(EAAユース第3期生)