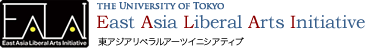2025年6月24日(水)、東京大学駒場キャンパス101号館11号室EAAセミナー室にて、EALAI研究セミナー第7回「惑星漢学(Planetary Sinology)の可能性を開く——東アジア藝文書院の実践と共に」が開催された。発表者は石井剛氏(総合文化研究科・地域文化研究専攻教授)である。

本発表において石井剛氏(EAA)は、中国研究をめぐる歴史的経緯と、その新たな展望としての「惑星漢学(Planetary Sinology)」の可能性について論じた。氏はまず、日本における中国研究が「漢学」「シナ学」「中国学」「東洋学」など多様な呼称のもとで展開されてきたことに触れ、その曖昧性が今日に至るまで学問的整理を困難にしてきたと指摘した。
また、「サイノロジー(Sinology)」という語が、単なる地域研究にとどまらず、本来的には普遍的知の体系を目指していたことに注目し、近代日本における「漢学」の成立や、漢文学との関係、さらには「中国」や「チャイニーズ」という語の多義性を歴史的・政治的文脈から再考した。とりわけ、現代における「中国」という概念の不確かさ――中華人民共和国、台湾、華僑・華人社会などの多層的実態――が、サイノロジーの枠組みを根本から問い直す契機となっていることを論じた。
こうした錯綜する知的状況に対して、石井氏は「惑星的思考(planetary thinking)」の導入を提唱する。それは、近代西洋が構築してきた普遍的知の体系に対し、東洋的知からの「巻き返し」を試みるものであり、テキスト読解を中心とするリベラルアーツ的実践に根ざしている。惑星的思考は、気候危機や生態系の崩壊といったグローバルな問題を背景としつつ、知を関係性の網の中に位置づけ直すための視座を提供する。
その実践の場として、哲学・文学・歴史学といった諸分野が横断的に交錯する「東アジア藝文書院(EAA)」の活動が注目される。そして、感覚=サイノロジーを周縁的知にとどめるのではなく、異なる普遍が交錯し、新たな思考が生成される契機として再構築することの意義が強調された。

(張子一 総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程学生)
2025年6月24日(星期三),东京大学驹场校区101号馆11号室的EAA研讨室举办了第七回EALAI研究研讨会,主题为“开启惑星汉学的可能性——与东亚艺文书院的实践同行”。此次主讲人为东京大学大学院综合文化研究科地域文化研究专攻教授石井刚。
在本次报告中,石井教授围绕中国研究的历史进程,探讨了作为新视角的“惑星汉学(Planetary Sinology)”的理论与实践可能性。他首先指出,近现代日本的中国研究在“汉学”、“支那学”、“中国学”与“东洋学”等多种名义下多线发展,但其学术定位至今仍未获得统一,造成理论上的模糊与整理上的困难。
随后,石井强调“汉学”概念并非适用于区域研究的范畴,而属于原本志在建构普遍性知识体系的学术传统。他进一步梳理了“汉学”在近代日本的形成过程,以及与汉文学的关系,辅以“China”、“Chinese”等概念在历史与政治语境中的多重含义。特别是在今日,“中国”一词已包含中华人民共和国、台湾、海外华侨与华人社群等多重现实,其概念的模糊性,已迫使传统“汉学”框架本身面临根本性反思。
面对这一复杂多元的知识局势,石井提出“惑星的思考(planetary thinking)”作为回应。这是一种以文本细读为核心的自由学艺实践,旨在对抗西方主导的普遍知识体系,寻求以东方知识进行“反击”的可能性。在气候危机与生态崩坏等全球性问题日益突出的当下,惑星思考也为重新理解知识与关系网络提供了全新视角。
报告最后,石井特别强调“东亚艺文书院(EAA)”作为一个汇聚哲学、文学与历史学等跨学科知识的实践平台,在这里,“汉学”不再被视作边缘之学,而是作为相对于现行西洋式的“普世性”而存在的另一种普遍性,从而成为促成新思维出现的重要契机。
(张子一,东京大学综合文化研究科地域文化研究专攻博士课程学生)