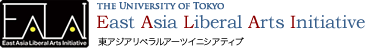2025年5月29日、第6回EALAI研究セミナーが開催された。
発表者は、比較文学比較文化が専門の、前島志保氏(総合文化研究科教授)。
発表テーマは「座談会記事はなぜ批判されたのか—―〈女・子どもの文体〉の成立と定期刊行物 における〈声〉の位置づけ」であった。

現在、多様なSNSの発達により、誰もがいつでも、自分の意見や主張を世界に対して発信している。しかし、こうした状況は真に自由で民主的な議論の場を提供しているのだろうか。前島氏の発表は、文体と性差、社会階級、権力、民主主義との間に取り結ばれてきた関係に迫り、こうした現代の状況を顧みさせてくれるものだった。
主に1920年代から婦人雑誌を中心に掲載された座談会記事は、30年代に総合雑誌や新聞でも大きな人気を博したが、「大衆的な編集手法」として批判されもした。なぜ、座談会記事が女性向けの雑誌(婦人雑誌)で、早期に、そして積極的に取り入れられ、その後、批判の対象となったのだろうか。この点について、前島氏は、定期刊行物の中で用いられた文体に特に注目しつつ、考察された。
19世紀後半には様々な口語文体が試みられ、各口語文体の性質や序列が明確ではなかったが、1904年使用開始の国定国語教科書に口語常体(「だ・である」体)と口語敬体(「です・ます」体)が正式な口語文体として指定されると同時に、書き言葉(筆術体)としての序列が、文語体、口語常体、口語敬体の順とされ、口語敬体は談話体とみなされるようになった。そしてこれに呼応するかのように、中等教育以上を受けた男性を主たる対象読者として想定した総合雑誌は口語常体を、この頃から明確に女性読者を対象とするようになった婦人雑誌は口語敬体を、それぞれ使用するようになる。つまり、婦人雑誌は女性読者を知的に一段低い存在と規定するようになったのだ。
話し言葉をそのまま記述する会話体や談話体、すなわち「〈声〉を響かせた文章」は明治半ばまで少なくなかったが、個人が一貫した立場から論じるという近代的批評観が導入されてからは、対話体、及び談話形式の記事は減少していった。さらに、国定教科書制定に伴う口語敬体への認識の変化により、「です・ます」体で書かれた談話記事は、記事ジャンルとして下位に位置付けられ、「女性」的とみなされるようになった。こうした文体の使い分けと序列化は、報道や文学における文章の近代化や雑誌の性差化とも連動していた。以降、婦人雑誌は談話体を駆使した記事ジャンルを発展させていき、このことが、女性雑誌での座談会記事の早期からの、そして積極的な連載につながっていく。
座談会記事が大きな人気を博しつつも批判されるようになった第一の理由は、座談会記事に象徴される「声の文化」の復権は、20世紀初めに成立した文体秩序の攪乱、すなわち近代的批評観への冒涜とみなされたことにあると考えられる。このほかの要因としては、次第に「談話記事」であることが明記されなくなることで、談話体が媒体として〈透明化〉し、「実際の談話の再現・記録」と読み取られ、解釈されるようになったことにより、事実性の混乱や文責の曖昧化を招いたこと、さらには、誰でも参加可能であり、「素人」も意見表明可能で、ある程度専門領域や性差・社会階層を越えた対話が可能であったこと(「知の民主化」)が、様々な規範の「侵犯」とみなされたことが挙げられる。
本セミナーは、会場、オンラインともに多くの人が集まり、関心の高さがうかがわれた。発表後には、座談会にはどのような人が出席し、どういった場所で行われたかなど、具体的なものから専門的なものまで、活発な質問が出された。
前島氏の、あらゆる雑誌や文献を渉猟し多角的に論ずる射程の広さ、記事の文体調査における定量的な手法とテクスト分析の融合、議論をまとめあげる洞察力に圧倒された1時間だった。個人的には、「知の民主化」という概念が印象に残った。座談会では「誰でも」「何でも」言うことができたのか、すなわち、人選や設定、テーマなどに権力が作用していなかったかということ。合わせて、「誰でも何でも」言える(ように見える)ことが「知の民主化」と言えるのか否かということ。発表と質疑応答で提起されたこれらの問題は、現代にも通じていると言えよう。

EALAI TA